「読む」から「聴く」読書へ。老眼と読書離れで見つけた、Audibleという新しい楽しみ。
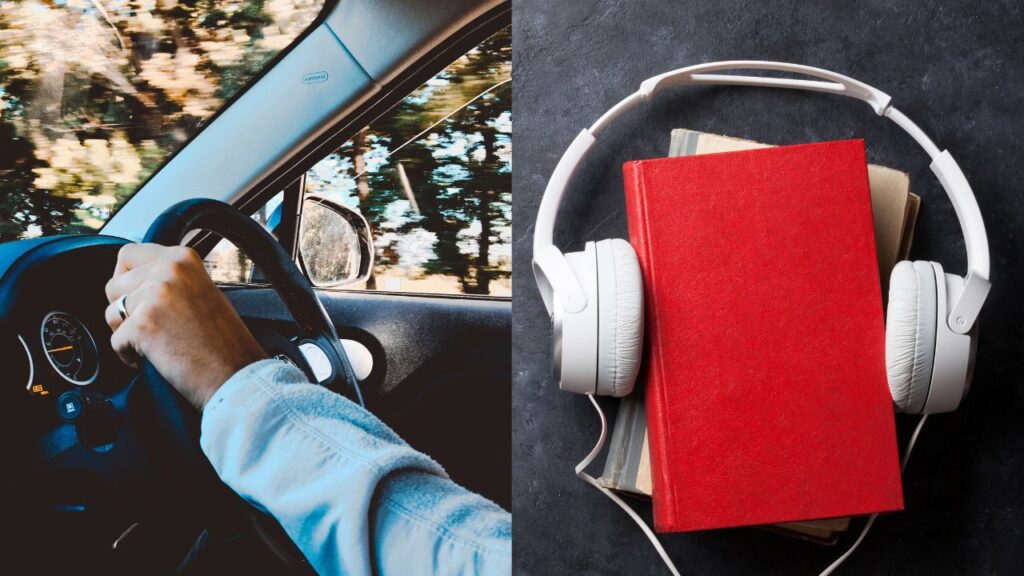
エンタメ系のサブスクは一通り試してきました。YouTube Premium、Kindle Unlimited、Amazon Music Unlimited、Spotify...。新しいサービスが好きなミーハー心と、少しでも生活を豊かにしたいという思いからです。
しかし、その中でも「読書」だけは、もう一度あの頃のように楽しむことを諦めかけていました。
かつての読書好きが、本を「読めなく」なった理由
15年ほど前、毎日片道1時間半の電車通勤をしていた頃は、私の大切な読書タイムでした。しかし、ここ石川県での生活は車移動が99%。ハンドルを握っている時間に本は読めず、いつしか読書の習慣はすっかり消えてしまいました。
「Kindle Unlimited」はお得だと感じつつも、越えられない壁がありました。
- 老眼の壁: 小さなスマートフォンの画面で文字を追うのは、正直しんどい。
- タブレットの壁: 読書のためだけに持ち歩くには、サイズ感と重さがしっくりこない。
「読みたい」という気持ちはありながらも、ライフスタイルの変化と身体的な問題が、私を本から遠ざけていたのです。
半信半疑で始めた「聴く読書」Audible(オーディブル)
そんな中、Amazonを開くたびに目につく「Audible 3ヶ月無料キャンペーン」の文字。「新しいことを試すチャレンジ精神を失ってはいけない!」と一念発起し、半信半疑で「聴く読書」を試してみることにしました。
車社会の石川で、「ながら時間」をインプットの時間に変えられるかもしれない。淡い期待を胸に、私のAudible体験が始まりました。
最初の壁と、見えてきた光明
まず私が聴いてみたのは、人気ランキング上位にあった吉田修一さんの『国宝 上 青春篇』。しかし、これがなかなかの強敵でした。一冊をまるまる聴き終えるには、かなりの時間が必要。これは本を読むときも同じですが、音声だと集中力が続かず、話が頭に入ってこない...。
「ながら聞きで内容を理解するのは、思ったより難しいのかもしれない」
あえなく途中断念です。「やっぱり合わないかな…」と思い始めた頃、次に選んだ一冊が私のAudibleへの印象を180度変えてくれました。
安藤玉恵さん著『とんかつ屋のたまちゃん』です。
著者である安藤玉恵さんご本人が朗読されており、まるで質の高いラジオドラマを聴いているようでした。この本は、目で「読む」よりも耳で「聴く」方が、その魅力が何倍にも増すタイプの作品だと感じました。
そして最高の出会いへ!車を降りてからも聴き続けた一冊
すっかり「聴く読書」のコツを掴んだ私は、営業車での移動時間に何冊か試しました。そして、久しぶりに「車を降りてからも続きが聴きたい!」と思える、衝撃的な一冊に出会います。
宮島未奈さん著『成瀬は天下を取りにいく』です。
主人公・成瀬あかりの唯一無二のキャラクターに、私は一瞬で心を鷲掴みにされました。何より、主人公の独特な喋り方や口調を、音声で実際に「聴ける」こと。これこそAudible最大のメリットだと確信しました。ページをめくる手が止まらなくなる、あの感覚が、「再生を止めるのが惜しい」という形で私に戻ってきたのです。
夢中で聴き終え、調べてみたらなんと「2024年本屋大賞」受賞作。納得しかありません。続編の『成瀬は信じた道をいく』も最高でした。読後の爽快感と、「私も明日からまた頑張ろう!」と思えるエネルギーをもらえる、素晴らしい作品です。
まとめ:「読む」から「見る・聞く」時代へ。体験から見えたこと
今回のAudible体験は、私にとって単なる趣味の復活以上の大きな気づきを与えてくれました。それは、情報の伝え方、そして受け取り方が大きく変わってきているという事実です。
「活字離れ」と言われる若い世代にとって、情報はもはや「読む」だけのものではありません。「聴く」、そして「見る」ことによって、より直感的に、より深く情報をインプットするスタイルが主流になっています。これは、決してネガティブな変化ではなく、時代の進化だと私は捉えています。
この変化は、私たちBCプランニングが事業として取り組んでいることと深く結びついています。
私たちは、建設業界の深刻な人手不足という課題に対し、Webサイトや動画制作を通じてソリューションを提供しています。仕事のやりがいや現場の熱意は、文字だけでは伝わりきりません。動画で職人の技術を「見て」、インタビューで働く人の声を「聴いて」もらう。そうすることで、若者が直感的に建設業の魅力を理解し、興味を持つきっかけを創り出せるのです。
Audibleが私の読書体験をアップデートしてくれたように、私たちもWebと動画の力で企業の「伝え方」をアップデートし、未来を担う人材との架け橋になりたい。今回の「聴く読書」体験は、そんな私たちの使命を再認識させてくれる、貴重な機会となりました。


